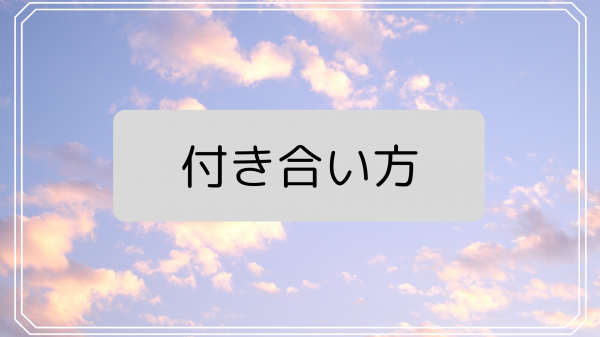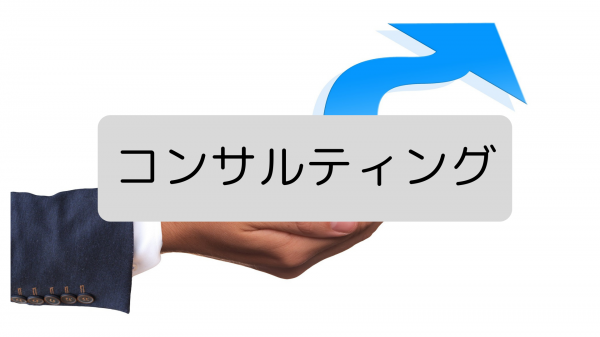この記事では以下の事が分かります。
①脚質の調べ方
②調べた脚質を予想に活かす方法
各馬の脚質を判断するのって意外と難しいですよね。
あなたも「え?この馬が逃げるの?」とか、
「何でこの馬こんな後ろにいるんだよ!」
などと想定通りにいかなかったことはありませんか?
レースの展開や流れが想定と変わってしまうと馬券は当たりません。
今回はそんな脚質について説明していきます。
目次
【決定版】脚質の調べ方

脚質を考える際に必要なファクターは6つあります。
①過去のレースのコーナー通過順
②枠の並び
③コース形態
④騎手の特徴
⑤通過ラップ
⑥陣営のコメント
各馬の脚質を調べる際は、上記6つのファクターを総合的に考えます。
以下で詳細に説明しますね。
過去のレースのコーナー通過順
脚質の調べ方として最もポピュラーな方法です。
しかし気を付けるポイントがあります。
それは出走馬の違いによりコーナーでの通過順は容易に変わってしまうという事。
例えば、今まで逃げていた馬でも自分よりテンが速い馬ばかり揃ったレースでは逃げられなかったり、テンが決して早くない逃げ馬でも、他に逃げたい馬がいなければすんなりとハナを切れたり。
このように出走馬の兼ね合いによって簡単にコーナーの通過順は変わります。
ですので出馬表に書いてあるようなコーナーの通過順はあくまで参考程度。
後述するファクターも取り入れて総合的に考えるのが一番です。
②枠の並び
外枠の馬は内枠の馬より最低でも1馬身前に出なければ先行出来ません。
1馬身というのは0.2秒です。
その為、枠の並びからイメージを膨らませれば各馬の脚質もすんなりと見えてきたりします。
また後述する「コース形態」や「騎手の特徴」も踏まえれば、より正確に各馬の脚質をイメージする事が出来ますよ。
③コース形態
各競馬場やその距離毎によるコース形態によって脚質が読みやすい場合があります。
例えば札幌芝1800mは、スタートから1コーナーまで185mしかありません。
基本的に各馬1コーナーに入ったら隊列は落ち着く為、内枠の馬が圧倒的に逃げ、先行しやす事になります。
このようにコース形態を考えるだけで、各馬の脚質が決まりやすい場合もあるのです。
④騎手の特徴
各馬の脚質は騎手によっても大きく影響を受ける場合があります。
ポジションを積極的に取りに行く騎手、インコースを突く騎手、折り合い重視の騎手。
騎手の乗り方ひとつで各馬の脚質も決まる部分がありますので、是非とも注目してみて下さい。

⑤通過ラップ
脚質の調べ方としてラップタイムを参考にする方法があります。
ラップというのは時計の事で、競馬新聞やJRAのHPにも書いてある通過タイムの事です。
そして脚質を考える際に最も注目すべきラップはテンの3Fです。
なぜなら、テンの3Fまでには基本的にペースは落ち着き位置取りは完成されているから。
その他には、各馬のレースタイムから上がり3Fのタイムを引いた通過ラップも参考に出来ます。
例えば、1600mのレースとしてゴールタイムが1分40秒、上り3F が33.5でした。
このゴールタイムである1分40秒から上がり3Fの33.5を引きます。
それによりスタートしてから1000mまでの通過タイム1分0.5という事が分かりますよね。
基本的には最初の3Fも、1000mの通過タイムでも、その間で極端に競馬が動くことは稀ですので、このタイムが指標となって逃げるのか先行なのか差しなのか判断が付くはずです。
しかし競馬においてタイムというのは非常に曖昧で、競馬場毎によってタイムの出方は異なりますし良馬場、重馬場でも変わってきます。
またレースの流れ一つでも大きくタイムは変化しますので、その点は注意して下さい。
⑥陣営のコメント
重賞などの大きなレースだと各陣営や騎手がレースに対してコメントをします。
「どの枠でも逃げるつもり」
「番手でも競馬が出来る」
「前に壁を作ってレースを進めたい」
などなどです。
このようにレースの戦法について関係者からコメントが聞かれる事が多々ありますので、そのコメントも参考にしましょう。
しかし逃げ宣言をしていても実際は全然逃げなかった。
というような事も珍しくないので、こちらもあくまで参考程度ですね。
調べた脚質を予想に活かす方法

それでは脚質の調べ方が分かった所で、予想への活かし方をご紹介します。
脚質から展開を想定する事で各馬の有利・不利が読める
結論から言います。
各馬の脚質は展開を想定する為に考えます。
競馬における展開というのは、スタート~ゴールまでの流れを一纏めにしたもの。
もっと簡単に言うとレースの形の事です。
レースがどのようなペースで流れ
各馬がどの位置で競馬を行い
直線どのような形でゴールを迎えるのか。
そのスタートからゴールまでの形が展開なのです。
そしてこの展開、レース結果に直結する程重要なファクターです。
何故かというと、展開によってそれぞれの馬には有利・不利が生まれるから。
そしてその有利・不利で結果が決まる事も良くあります。
展開を読まずして馬券は当たらないのです。
展開の想定方法
展開を想定するのにあたって考えるべきポイントは以下の2つです。
①ペースの設定
②位置取りの想定
この2つを考えれば、展開は読めます。
以下で詳細に説明しますね、
ペースの設定
まずはレースのペースを考えます。
何故なら、レースのペースが遅いのか早いのか?
それが読めるだけでも各馬の取り捨てが出来るからです。
スローペース=前の馬が有利
ハイペース=後ろの馬が有利
もちろん状況次第ですが、基本的には上記のようなアドバンテージがあります。
そしてレースのペースを設定する方法は、逃げ馬を考える事。
逃げ馬がいない=スローペースになりやすい
逃げ馬が複数いる=ハイペースになりやすい
逃げ馬が溜め逃げをするタイプ=スローペースになりやすい
逃げ馬が話し逃げをするタイプ=ハイペースになりやすい
どの馬が逃げるか?
逃げ争いはどうなるか?
逃げた馬はどのようなペースで逃げる特徴があるか?
この辺りを抑えて、まずはペースを読んでいきましょう。
位置取りの想定
ペース設定が出来たら、次に各馬の位置取りを想定をします。
参考にするファクターは上記で説明した「脚質の調べ方」と一緒です。
①過去のレースのコーナー通過順
②枠の並び
③コース形態
④騎手の特徴
⑤通過ラップ
⑥陣営のコメント
しかし展開と合わせて考えるべき非常に重要なファクターがあります。
後述で詳しく説明しますね。
【超重要】トラックバイアス
展開と同じかそれ以上にレース結果に直結するファクター。
そして展開とセットで考える事で大方予想が出来上がってしまうもう一つのファクター。
それはトラックバイアスです。
トラックバイアスとは馬場の偏り
競馬場というのは基本的に陸上のトラックのような形をしています。
そして陸上の200mや400mを思い出してください。
1レーンから8レーンまでありますが、それぞれスタート位置が異なります。
これは常に同じレーンを走る特性上、コーナーでのロスが生じる事への配慮です。
つまり陸上では、横一列のスタートで同じレーンを走ると距離のロスが無い1レーンが有利で8レーンが不利という構造的な問題があるという事です。
まぁこれは当たり前の話ですよね。
それでは競馬に置き換えて話しをします。
競馬は最大で18頭ものの馬が一緒に走りますよね。
しかしスタートは横一列です。
そしてスタートをしてからは各騎手が思い思いの位置を取り競馬が進む。
その結果コーナーではロスがある馬とない馬に分かれます。
競馬というのはハナ差クビ差というように、非常に僅かな差で着順が大きく変わる為、決してコーナリングでの距離ロスは無視できないのです。
つまり走る位置によって有利不利があるという事。
その馬場による偏りこそがトラックバイアスです。
※上記の事からコーナーを回る際に有利不利が生じる事が分かったと思います。
しかし「内枠の馬だけしか来ないのか?」
というとそんな簡単なものでもありません。
外枠の馬でも、後方から外を回して差してくる馬でも勝つときは勝ちます。
具体例を挙げますと
・開催が進むにつれて芝が剥がれていき、ロスがあっても芝が綺麗な所を走れる馬が有利
・ロスがあってもペースが速かった為、差し馬に向いた展開
・そもそも馬の能力が違った
上記のように条件次第でトラックバイアスの中身や重要度も変化しますので、その他の要素と比較することが大切です。
トラックバイアスの調べ方
トラックバイアスの調べ方は当日(午前中の早い時間帯のレースで参考になるレースが無い時は、前日または先週のレースを参考にする)のレース映像の分析です。
あなたが予想するレースが芝なら芝の全レース、ダートならダートの全レースのレース映像を全て分析してトラックバイアスを調べます。
具体的な方法は、
1~3着馬の道中、4コーナー、直線での位置を分析します。
例えば、当日の殆どのレースで逃げ馬やインコースを走った馬ばかりが人気関係なく1~3着を独占していたら、明らかにインコースが有利です。
このようにまずはレース映像の分析をして、あなたが予想するレースのトラックバイアスを判断しましょう。
※トラックバイアスを判断する際の注意点
①馬の能力を加味する
→インコースが有利な馬場でも外を回って勝ち切る能力が抜けた馬はいます。
馬の能力を考えずに好走した馬の位置取りだけで馬場状態を判断すると、誤った把握となってしまいます。
②ペースを考慮する
→インコースが有利な馬場でもハイペースの前崩れの展開になれば外の競馬になります。
逆に外伸び馬場でもペースが落ち着きすぎると結局は前が残ります。
馬の能力同様、ペースも考慮して馬場状態を把握しましょう。
③内回りや外回り、距離などでも馬場状態は変化する
→仮にインコースが有利であったとして、内回りや長距離戦ではより顕著にその傾向がみられたりします。
この馬場状態の微妙な変化はその日その日で変わりますので、より詳細に見ていく必要があるのです。
④映像での馬場状態の把握を簡略化する
→馬場状態を把握する際、道中の映像を飛ばし直線だけで判断するのは簡略化の為にやってしまいがちです。
しかしそれでは馬場状態の把握が不完全なものとなってしまいます。
なぜならスタート~4コーナーまではロスなく乗って直線だけ外に出すというパターンが意外と多いからです。
またスタートで出遅れているかもしれないですし道中で不利があるかもしれません。
そのため簡略化はせず映像を分析する癖をつけましょう。
展開とトラックバイアスの相関性について
展開とトラックバイアスはセットで考えましょう。
何故なら、展開とトラックバイアスはレースの結果を左右する程の重要なファクターだからです。
その為、レースの予想段階から展開とトラックバイアスの想定を完璧にしておけば、後はそこに当てはめるだけ。
仮に「インコースが有利な馬場状態でスローペース」と想定されるのであれば、
逃げ・先行馬と内を走れる馬を中心に予想を組み立てれば当たります。
もちろんそのような展開と馬場状態で設定しても、能力の違いで好走する馬はいるかもしれないので、各馬の能力判断は必要ですが、ある程度この段階で予想は絞れます。
だって外枠の差し・追い込み馬はこの展開、トラックバイアスを覆すほど能力が長けていないと好走は出来ないからです。
そして各競争馬同士はあなたが思っているよりもずっと能力差はありません。
そのため展開と馬場状態の想定をしっかりと行えていれば、それだけで予想は当たるといっても過言ではないのです。
【具体例】2019年安田記念
それでは実際のレースを使って説明していきます。
それは2019年の安田記念です。
個人的にはアエロリットから買って当たったレースなのですが、この日の東京芝はインコースが極端に有利なバイアスでした。
それを表すように東京の8、9レースは1,2着がどちらも内埒沿いを走っています。
8レースは1着が6番人気、2着が5番人気。
9レースは1着が10番人気、2着が3番人気という決着になっています。
そして安田記念の結果でもその傾向は顕著に出ていましたよね。
1着のインディチャンプは4,5番手の埒沿い。
2着のアエロリットは逃げ馬。
4着のグァンチャーレは2番手の埒沿いで単勝103倍。
5着のサングレーザーも埒沿いを走っています。
その中で3着のアーモンドアイのみが外を回って追いこんできています。
またこの日は高速馬場で時計の割に逃げ・先行馬が有利で展開利も前にありました。
レース後は負けた要因としてスタートでの不利が大きく取り立てられていましたが、インが有利な馬場で外を回らされたことが一番の敗因。
以上のようにトラックバイアスと展開から考えれば、レース結果がより鮮明に見えてくるはずです。
【まとめ】脚質を調べ展開の想定へ予想を繋げれば、あなたのスキルは確実に磨かれます!

いかがだったでしょうか?
あなたが考えていた脚質の調べ方とはまた違った話だったと思います。
最初の内は各馬の脚質を考えるのは難しいです。
しかし数をこなしていけば経験的に自分なりの見え方が必ず出てきます。
脚質から考えてレースの展開を正確に想定できる。
これだけであなたの競馬予想は飛躍的に成績が向上するはずです。
あなたの予想の参考になれれば幸いです。