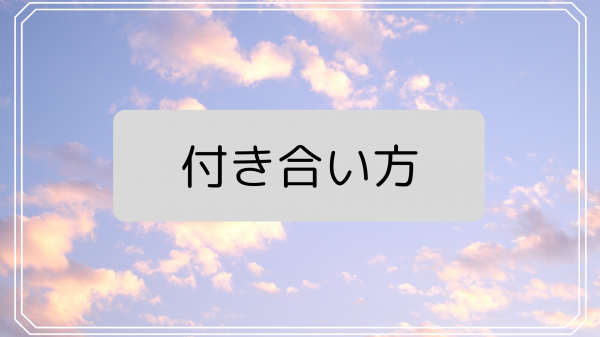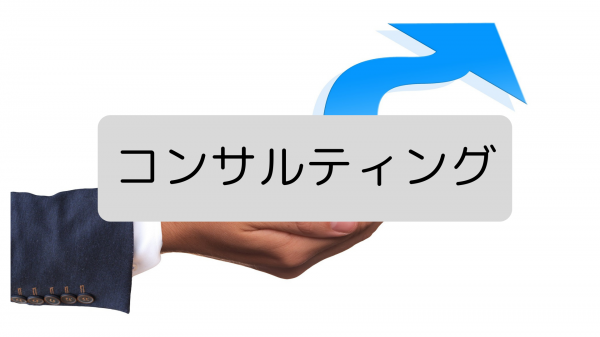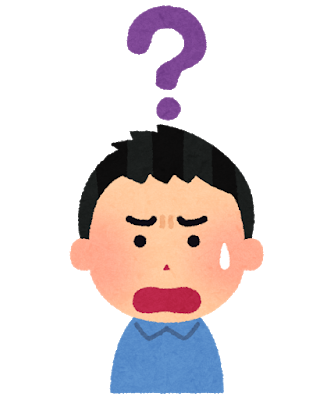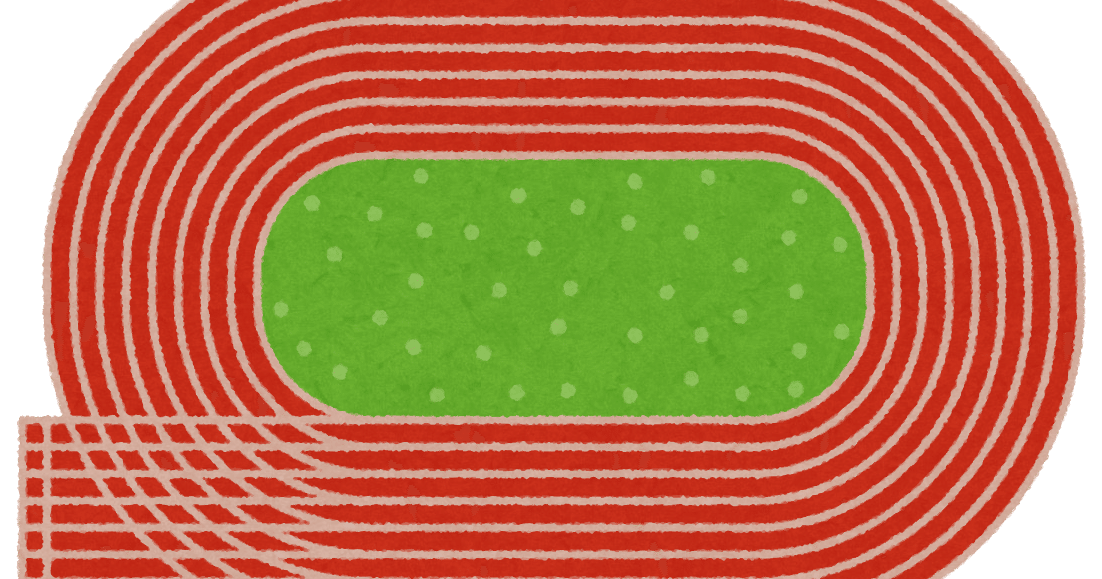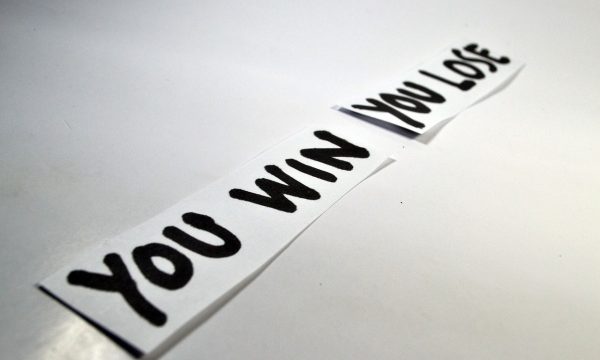と疑問を抱えているあなたの悩みを解決出来る記事を書きました。
なぜなら、これから紹介する「競馬予想の仕方」を学び実践した事で年間回収率は100%超えを達成し9800円の投資にて最高払戻金288万円を獲得するまでに至ったからです。
そしてこの記事では私が考える「競馬予想における最重要ファクター4選」を全て紹介しております。
競馬初心者のあなたでも理解出来るよう分かりやすく説明しており今からでもご自身の予想に活かせる再現性の高さにも拘って記事を作りました。
これらの記事を読み終える事で「根拠ある競馬予想の仕方」を身につける事が出来、今からでも予想スキルの底上げが可能となります。
目次
1.【4つのファクター】競馬予想の仕方を徹底解説

私の予想ファクターは下記の4つになります。
・トラックバイアス
・ラップ適性
・展開バイアス
・各馬の能力比較
1つずつ解説していきますね。
①結果に直結するトラックバイアスを理解しよう
まず始めはトラックバイアスという予想ファクターから説明します。
競馬を予想する上で考えるファクターは様々あると思いますが、個人的にこのトラックバイアスという予想ファクターが最も大切だと思っています。
初心者のあなたでもなるべく分かりやすく説明しますのでぜひ最後まで読んでいってください。
トラックバイアスとは?
トラック=馬場
バイアス=偏り
という意味でトラックバイアスは馬場の偏りという意味です。
そしてこの馬場の偏りというのは走る位置による有利不利の事を指しています。
例えば、インコースが有利な馬場であれば逃げ馬が止まらなかったり、外が伸びる馬場では追い込み馬が届いたりとそのトラックバイアスに恵まれた馬というのは好走する確率が飛躍的にアップするのです。
特に能力が拮抗しやすくなる上級条件(重賞)ではトラックバイアスに恵まれる必要性は特に高くなりますね。
よって馬場の偏りを見極めどの位置を走る馬が有利か不利かを考えるファクターがトラックバイアスというものになります。
何故トラックバイアスが生まれるのか?
陸上のトラックというのは下図のような形をしていますよね?
そして200mや400mではスタート位置が各選手で異なります。
これはコーナーでのロスを考慮して各選手フェアに走る為の対応です。
ここで競馬に話を戻しますが、競馬場というのも陸上のトラックのような形をしています(各競馬場で個性はありますが)。
しかし競馬では最大で18頭もの馬が横一列でスタートします。
その為、コーナーでのロスというのが必ず生まれるのです。
そして競馬の着差というのは、ハナ差やクビ差といった馬の体の部位毎に区別しなければいけない程わずかな差で決着します。
つまりコーナーでの1.2頭分といったロスはレース結果に大きな影響を与えるのです。
これが基本的なトラックバイアスという概念の正体になります。
トラックバイアスの調べ方
トラックバイアスを調べる方法はレース映像の分析です。
そしてレース映像を分析する際のポイントは1~3着馬の位置取り。
上記のような形でトラックバイアスを判断出来ます。
予想レースのトラックバイアスの判断方法
トラックバイアスを予想に活かす為には、あなたが予想するレース自体が「内が伸びるのか?」、「外が伸びるのか?」などのバイアスを判断する必要があります。
そのバイアスを判断するには、当日の予想レースと同条件のレース映像を分析する事です。
例えばあなたが芝2000mの11Rを予想するとします。
そうしたら当日の芝のレースの映像を全て分析して下さい。
何故なら、レースの結果を決めるのはトラックバイアスだけではないから。
もちろんトラックバイアスがレースの結果に直結する重要なファクターである事は変わらないのですが、競馬は様々なファクターによって作られています。
その為1、2Rだけ見ての判断ではトラックバイアスの影響なのか、その他の影響なのか判断が出来かねるのです。
僕でさえも当日は芝なら芝、ダートならダートのレース映像を全て分析し、トラックバイアスを判断しています。
開幕週やコース替わりはチャンス
【開幕週】
JRAでは10の競馬場があり大体一、二か月月毎に開催場所が変わっていきます。
その際の始めの1週目を開幕週と呼んでいるのです。
芝は生き物ですので休む必要があります。
そのため開催日以外の日には、JRAの職員により芝は生育に努めます。
その状態が続いてレースを迎えますので、開幕週の際は非常に馬場コンディションが良好なのです。
【コース替わり】
開催が進めばコース替わりも行われます。
コース替わりとは、馬場のコンディションを保つという馬場の保護の観点から定期的に内埒を数メートル外に出して痛んだ箇所を走らずになるべく馬場の良いところを走るようにする工夫の事です。
競馬場毎に開催している期間が違うので一概には言えないのですが大体は一か月に一回。
二か月近く開催しているときは二回ほど、コース替わりは行われます。
つまり開幕週やコース替わりというのは、馬場の状態が非常に良好ということ。
その為、逃げ・先行馬や内枠の馬が有利になりやすい傾向があるのです。
実際に開催前半では逃げ馬の勝率、連対率、複勝率が全て開催後半を上回り
逆にマクリの馬は勝率、連対率、複勝率が全て開催後半を下回るといったデータもある位ですからね。
ですので開幕週やコース替わりの週は狙い所が絞れる為チャンスなのです。
開幕週=逃げ・先行馬や内枠の馬が有利になりやすいというのはあくまで傾向
開幕週で馬場が綺麗だから逃げ・先行馬や内枠の馬が有利になりやすい。
上記の事はあくまで「そうなる傾向が強い」というものです。
絶対的な話ではもちろんありません。
開幕週でも外を回す追い込み馬が来ることももちろんあります。
逆に最終週で内の馬場が荒れていたとしても逃げ・先行馬が残るレースというのも珍しくありません。
ですので一概に「開幕週だから」という理由だけで判断するのは危険だという事を頭に入れておいて下さい。
開幕週とはいえ、レース映像を分析しトラックバイアスを見定める必要は必ずあるのです。
展開バイアス想定
つづいては展開の想定です。
展開とはスタートしてから道中、3・4コーナー、直線での各馬の位置取りや隊列、レースの流れなどを一纏めにしたレースの形の事。
この展開もトラックバイアスと同じくレース結果に直結する極めて重要な要素なのです。
そして展開はトラックバイアスとセットで考えるのが重要。
ハッキリ言いますが、トラックバイアスと展開をセットで考える事で大方予想は出来上がります。
展開の想定方法
流れとしては以下の通りです。
レースのペースを設定
↓
各馬の位置取りを想定
↓
トラックバイアスと合わせて考え、有利なポジションを考える
1つずつ解説します。
レースのペース設定
まずはレースのペース、流れがスローペースなのかミドルペースなのかハイペースなのかを考えましょう。
【スローペース】
・レース前半のタイムがレース後半のタイムより1秒以上遅い場合
・後傾ラップで上りの時計が速い
【ミドルペース】
・レース前半のタイムとレース後半のタイムとで差が少ない
・レースのラップが一定で前後半のふり幅が少ない
【ハイペース】
・レース前半のタイムがレース後半のタイムより1秒以上早い場合
・前傾ラップで上りに時計を要する
ペースの判断基準は上記が一つ目安となります。
※タイムのみでペースを判断するのは不十分
1000mの通過タイム59秒だからハイペース。
800m通過が48秒だからスローペース。
といった形でラップタイムのみでペースを判断する場合は良くあると思います。
ただこの数値はあくまで目安程度のものと考えて下さい。
何故なら、タイムの出方はその日の馬場の影響を強く受ける為基準タイムに一貫性が持てないからです。
馬場は生き物の為、日によって時間によって馬場状態は変化していますし競馬場毎でも時計の出方は変わっています。
またもう一つの理由としては、ラップは先頭の馬のタイムの為隊列次第では後続の馬とタイムが全く異なる場合があるから。
これは大逃げの例が分かりやすいです。
逃げ馬が後続を10馬身以上離した大逃げを打ったとします。
そもそもラップというのは、先頭の馬が通過したタイムになりますので逃げ馬が早ければ当然ラップも早くなります。
しかし大逃げのように先頭だけが早く、2番手以降のペースは実際遅いという事は良くありラップ自体は早いも結果は前残りになったりもします。
ですので上記2つの点は注意してペースの判断を行って下さい。
そして各ペース毎に有利になる馬は下記の通り。
【スローペース】
・逃げ馬や先行馬、内枠でロスなく乗れる馬が有利
・差し馬や追い込み馬、外枠でコーナーロスがある馬は不利
基本的にスローペースでは前残りの競馬になりやすいです。
ペースが遅いという事は楽に道中を走れているということ。
そのため直線に入っても各馬余裕があるので前にいる馬も簡単には止まりません。
つまり前にいるだけでアドバンテージが生まれるのです。
これはロスなく乗ってこれる内枠の馬にも有利に働きます。
ですのでスローペースを想定したら逃げ馬や先行馬、内枠の馬の評価を挙げて予想を組み立てていきましょう。
【ハイペース】
・差し馬や追い込み馬、外枠でスムーズに競馬が出来る馬に有利に働く
・逃げ馬や先行馬はオーバーペースになりやすく不利
ハイペースのレースは前崩れの展開になりやすく外を回る差し・追い込み馬を中心に考えましょう。
特に今まで展開的に脚を余してきた馬の出番です。
追い込み一辺倒の馬はどうしても展開に左右されてしまい成績が安定しません。
しかしハイペースで差し・追い込みが決まる形になれば「力はあるが展開に恵まれてこなかった馬」の出番。
過去の着順で人気も落としやすいので、そのようなケースは積極的に馬券を買っていきましょう。
※直線の長いコースではスローペースだと瞬発力勝負になることもあります。
瞬発力勝負とは、上りのスピードを求められるレースの事で決め手勝負になりやすいです。
つまりペースが遅くてもギアチェンジが効く瞬発力勝負が得意な馬であればむしろ追い込みん出来るという事。
新潟競馬場の外回りや東京競馬場といった直線が長いコースでは、ペースが落ち着くと瞬発力勝負になり差し・追い込み馬が代頭することがあります。
特に新潟競馬場の外回りは瞬発力勝負になりやすく上りが32秒台の決着も珍しくありませんので一つのポイントとして頭に入れておきましょう。
ペースの判断
ペースを判断するポイントはズバリ逃げ馬です。
何故なら、逃げ馬のスタイルによってペースは決まるから。
スローペースに落として溜め逃げをするタイプの馬や道中ペースを緩ませずに淡々と逃げる馬など。
なのでまずは「どの馬が逃げるか」そして「その逃げ馬はどのようなスタイルで逃げを打つか」を考えましょう。
逃げ馬と言えど馬によって逃げ方は異なりますので、過去のレースを見て逃げ馬のスタイルからペースをまずは想定するのです。
各馬の位置取りの想定
続いては各馬の位置取りを想定します。
方法としては、脚質や枠の並びコース形態を考えてイメージする事です。
イメージと聞くと大雑把に聞こえますが、各馬の位置取りは厳密に考える必要はありません。
何故なら、トラックバイアスとセットで考えるからです。
例えば、インコースが有利なトラックバイアスでスローペースが想定できるレースがあったとします。
この時点で予想の中心になる馬は逃げ馬や内でロスなく乗れる馬。
ですので考えたい位置取りは、逃げと内ラチ沿い、好位になります。
そこまで絞れれば内枠の馬やその中でも先行できる馬に焦点が当たる為、後は上記で言ったようにイメージで想定が出来ます。
再度言いますが、展開はトラックバイアスとセットで考えます。
そしてトラックバイアスと展開によってレースの結果は大方が決まるのです。
騎手の特徴を考える
展開を考える上で騎手も重要なファクターになります。
何故なら、騎手にはそれぞれ特徴があるからです。
・積極的にポジションをとってくる騎手
・馬の気分に合わせて乗ってくる騎手
・インコースを突くのが上手い騎手
そのため騎手の特徴を理解し、
「この騎手がハイペース覚悟で逃げてくるかもしれない」
「この騎手でこの枠なら積極的にポジションをとりにいくだろう」
「この騎手が逃げたら他の騎手は不必要に追いかけていかない」
等を考える事でもペースの想定や各馬の位置取りがより明確になります。
各馬の能力比較
トラックバイアスと展開バイアスを掛け合わせれば各馬の能力比較も出来るのです。
一例を挙げます。
日曜日のメインレース東京競馬場の芝2000メートルの重賞を予想。
そのレースに前走が同じだった馬がいました。
Aという馬は前走2着で今回1番人気の馬、Bという馬は前走6着で今回は5番人気の馬です。
着差は0.2差。
これだけを見るとAがBより人気するのは当然ですよね?
しかしレース映像を分析したところAは逃げて2着、Bは大外から追い込んで6着でした。
レース内容に大きな違いがあります。
ここでその日のトラックバイアスを把握してみましょう。
そうするとその日の芝のレースでは逃げ馬やインコースを突いた馬が好走をしていることが分かりました。
インコースが有利なトラックバイアスだったという事ですね。
またそのレースは逃げ馬がAしかいなく楽に逃げれた展開バイアスもありました。
そこで次に今日のトラックバイアスを把握します。
すると今回は逆で外差しも決まるトラックバイアスでした。
また展開バイアスも逃げ馬が複数いてペースは速くなりそうです。
ここまでトラックバイアスと展開バイアスを判断出来ていれば、AよりBの5番人気の馬を買いたくはなりませんか?
少なくともAは危険な人気馬だという事が分かると思います。
因みに0.2差というと約1/1/2馬身差になりますが今回説明したレース内容では、これ位の着差は容易にひっくり返ります。
これがトラックバイアスと展開バイアスを把握した各馬の能力比較です。
競走馬同士の能力差はそこまで無い!
あなたが思っているほど競走馬同士の能力差というのはありません。
1つのトラックバイアスや展開バイアスだけでガラッと着順が変わるのは普通の事です。
数十年に一度ディープインパクトやオルフェーヴルといった歴史的名馬は存在しますが、そのような名馬は非常に稀ですからね。
そのため単純な能力比較のみでは予想としては不十分。
その事は常に念頭に置いて予想をするよう心掛けてみて下さい。
鵜吞みは禁物!やってしまいがちなダメな予想の仕方2選

僕がダメだと思う予想の仕方は以下の3つです。
①サイン予想
②データ予想
③人の予想に全乗っかり
因みにここで言う「ダメな予想」というのは長期的に見て競馬で負けてしまうであろう予想の仕方のことです。
詳しく後述していきます。
やってしまいがちなダメな予想の仕方①サイン予想
サイン予想とは、時事ネタであったり直近であった大きなニュースに関する事、プレゼンターに関連する数字などをレースに結び付けて行う予想の仕方になります。
そしてサイン予想はなぜダメかというと、その予想自体に全く根拠が無いからです。
競馬の予想スタイルは十人十色ですので基本否定はしたくないのですが、どうしてもオカルト的要素のみですからね。
しかし昔は違いました。
まずはサイン馬券の始まりについてお話しをします。
昔のサイン馬券は徹底した情報収集にあった
サイン馬券は、競馬評論家の高本公夫さんの予想手法が元祖と言われています。
この高本公夫さんという方は、元調教師の競馬評論家でありスポーツ紙で予想コラムを連載していました。
そのコラムで連載していた予想スタイルの特徴は何と言っても徹底した情報取集にあります。
高本氏が行っていた❝サイン馬券❞は、競馬場内外の情報を初め、厩舎の人脈や競走馬の生理的要素、はたまた馬主の経済状況やJRAの集客戦略に至るまで、ありとあらゆる方向から情報を集めて予想に活かすというものでした。
その為、現在主流になっているオカルト要素強めなサイン馬券とは一線を書いており、厩舎の勝負仕上げや競走馬の好走パターン等を分析した理論的な予想というわけです。
競馬の発展に伴いサイン馬券はオカルト的に変化していった
それでは高本氏のサイン馬券は何故、現代のオカルトチックなものになってしまったのでしょうか?
それは競馬の発展にあります。
競馬産業が発展していくにつれて、高本氏の情報元であった厩舎や競馬関係者が、競馬場近郊から郊外に新しくできたトレーニングセンターに移り変わっていったり、JRAの取材システムが変更になったりと以前のような情報収集が次第に出来なくなってしまったのです。
その為高本氏は、以前のような徹底した情報収取から作り出される唯一無二な理論的な予想では無く「JRAのレースは作為的要素がある」「枠順も操作されている」「競馬は八百長だ」
といった現代でも目にする根拠のない予想スタイルに変化してしまったのです。
また、このような根拠のない予想は誰でも言えます。
結果、高本氏の後を追うように根も葉もない事を言って競馬の予想を行う人達が増えてしまい結果、現代のサイン馬券という概念に切り替わってしまったと言われています。
実際のサイン馬券の一例
・【2012年有馬記念】 今年の漢字は「金」 優勝馬ゴールドシップ
これは有名なサイン馬券の一つです。
年の瀬に毎年発表されている今年の漢字。
2012年の今年の漢字は「金」でした。
そして、年の瀬の風物詩、有馬記念で勝った馬は名前に金(ゴールド)が付くゴールドシップ。
直線大外、別次元の足で追い込んできたゴールドシップは衝撃的だったのを覚えています。
・【2015年ジャパンカップ】 プレゼンター五郎丸歩の背番号15優勝馬15番のショウナンパンドラ
2015年は4年に一度のラグビーワールドカップが開催され、五郎丸歩選手が一躍時の人となりました。
その五郎丸歩選手がジャパンカップのプレゼンターとして来ていたのですが、その五郎丸歩選手の背番号は15番。
そしてジャパンカップを買ったショウナンパンドラの馬番も15番でした。
また、ショウナンの勝負服が日本代表のユニフォームにそっくりだったのも話題になっていましたね。
・【2014年有馬記念】 読売巨人軍終身名誉監督長嶋茂雄が来賓者として出席 勝ち馬ジェンティルドンナ 長嶋茂雄とジェンティルドンナは2月20日で誕生日が同じ
最後は2014年の有馬記念です。
この有馬記念は3冠牝馬ジェンティルドンナの引退レースとなっていました。
そして来賓者として読売巨人軍終身名誉監督長嶋茂雄が来ていました。
レースは見事ジェンティルドンナが好位から抜け出し、何ともドラマチックな結末を迎えたのですが競馬ファンを驚かせたのは他にもありました。
それは長嶋茂雄とジェンティルドンナの誕生日が2月20日で同じだったという事です。
改めて思い返すと出来すぎた話ですね。
やってしまいがちなダメな予想の仕方②データ予想
日本中央競馬会は1954年に創立されておりその歴史は60年以上になります。
あなたが競馬を始めるずっと前から競馬は行われていたのです。
そのため過去には膨大なデータが眠っております。
そのデータを使って予想を行うのがデータ予想です。
競馬予想で良く使われるデータ
ここでは実際によく使われるデータについて説明していきます。
あなたが参考にしているデータもあれば、あまり使ったことが無かったデータもあると思いますので是非参考にしてみて下さい。
・枠順によるデータ
まずは枠順です。
レースによって内枠の馬の方が成績が良かったり、枠番指定で3番枠の馬は2-2-1-5といった具合に成績が偏るケースがあります。
このデータはコースや開催時期の馬場状態等の影響を受けやすいため、データとして分かりやすく予想にも反映させやすいです。
・人気によるデータ
続いては人気です。
1番人気の成績が良い本命が強いデータもあれば
なぜか5番人気の馬の成績だけが極端に良い場合など特徴的なデータもあります。
オッズから馬を選ぶ際に便利ですね。
・年齢によるデータ
年齢もデータ化すると特徴を示す場合があります。
古馬と3歳馬との初対戦が多かったりするレースでは、使用頻度が高いのではないでしょうか。
3歳馬がいい成績のレースもあれば、
逆に人気でも3歳馬の成績が悪く4歳や5歳といった古馬のレースとなるデータも挙がります。
・厩舎によるデータ
美浦や栗東といった分け方でもデータにすれば偏りが見られる場合もあります。
また厩舎別で見ていけば
「藤沢厩舎はこのレースに強い」
「中内田厩舎と川田騎手のコンビは成績が良い」
「1200mの距離は安田厩舎の馬が好成績」
といった形でより詳細なデータを分析出来て予想に活かせますね。
・血統によるデータ
血統はいわば過去のデータの産物です。
「ディープインパクト産駒は瞬発力勝負に長けている」
「ハーツクライ産駒は重馬場適性が高く道悪競馬に適性がある」
「ステイゴールド産駒は長距離戦が得意」
などといった血統による特徴は、今までに産駒たちが走ったレース結果から導き出された傾向によるものです。
種牡馬の現役時代の特性ももちろんありますよ。
しかしベースは子供たちが走った過去の膨大なレース結果から分かった特徴によるものなのです。
・前走の成績やローテーションによるデータ
前走の距離別による成績やこのレースを前哨戦とした馬の成績は良い。
といった具合で前走の成績やローテーションもデータ化され予想に活かせます。
しかし最近の競馬の傾向としては、前哨戦の価値が少なくなってきており休み明けでも本番へ直行して結果を出すのが多くなってきております。
データが変化してきている場面なのかもしれません。
・位置取りによるデータ
続いては位置取りです。
「4コーナーでは5番手以内の馬の3着内率が高い。」
「10番手以降の馬が5年連続で勝っている。」
といった具合で4コーナーでの通過順や直線での位置取りで特徴を示す場合があります。
・コースによるデータ
コース形態やコース毎の距離でも特徴を示す場合が多いです。
「中山競馬場の芝2500mではスペシャルウィーク産駒の馬の成績が優秀」
「東京競馬場芝2400mでは1枠の馬の成績がトップ」
「新潟競馬場芝2000m外回りでは差し馬が有利」
などなどコースの距離別で見ていけば、より顕著なデータの特徴が分かってきます。
データ予想がダメな理由
僕が何故データ競馬をダメと言うのかというと、データはあくまでデータでしかない為それだけで予想をしては特別根拠がないからです。
・逃げ・先行馬の成績が優秀
・1~3番枠の馬の3着内率が50%を超えている
とは言え今回も同じ結果になるとは限らないですよね。
走るメンバーや頭数、騎手、ペースや馬場状態などレースの中身はまるっきり変わっています。
それなのに過去のレース結果の特徴を今回のレースに結び付けるのは意味が無いとさえ僕は思います。
ですのでデータ予想では「何故そのようなデータが出るのか?」という視点を持つ事が大切です。
内枠の馬の成績が良い
→開幕週でインコースが有利なバイアスになりやすい、頭数が少なくペースが落ち着きやすい、コース形態的に内枠の馬が有利になりやすい。
といった形でそのデータを裏付ける理由を自分なりに解釈できるのであればデータ予想もアリだと思います。
予想の仕方を確立し年間回収率100%を越えた僕が今思う事

結論から言うと、競馬で勝つ為には正しい知識と継続する力さえあれば誰でも結果を出す事は可能です。
僕は2011年に競馬を始めましたがもちろん最初から勝てていた訳ではありません。
当時はJRAのHPに書いてある過去のデータを参考に予想をしていましたが、全然当たらなかったですから。
その結果、自然と的中率を求めるようになってしまい1番人気ばかりを買うようになってしまいました。
当たらない→一番人気に逃げる→当たらない
完全に負のスパイラルが出来上がっており、なかなか抜け出す事も出来ていませんでした。
競馬で勝つ為の正しい知識が無いとただの養分
そうなってくると「流石にこのままではマズイ。ただの養分じゃん…」と思うようになり、初めて競馬を一から勉強し直しました。
色々な予想の仕方を研究し試行錯誤を経てようやく現在の考え方に辿り着いた感じですね。
それがこの記事で説明した下記になります。
・トラックバイアスの把握
・展開バイアスの想定
・各馬の能力比較
正しい知識を身に着けたら、ひたすら予想を磨く。
正しい知識を身に着けたらあとはやるだけです。
ひたすらレース映像の分析を行い予想スキルの向上を図ります。
僕も学校が終わって家に帰って来てから3時間以上は過去のレースを分析していました。
それこそ土日は丸一日ずっとレースを見ては予想をしての繰り替えしでした。
そのおかげで正しい知識を身に着けてから2ヶ月後には、初めての万馬券が的中。
その1ヶ月後には、800円で13万円の払戻金を獲得。
そのおかげもあって年間回収率100越えを達成出来るまでになれました。
まとめ
この記事のポイントを下記でまとめました。
【予想ファクター】
・トラックバイアスの把握
・展開バイアスの想定
・各馬の能力比較
【ダメな予想ファクター】
・サイン予想
・データ予想
※データ予想に関しては、そのデータを裏付ける理由を自分なりに解釈する必要があります。
あなたの予想の参考になれれば幸いです。