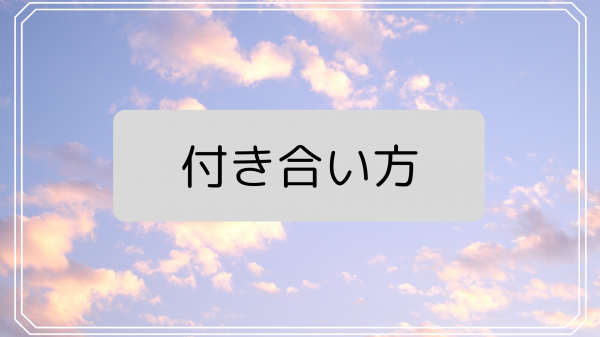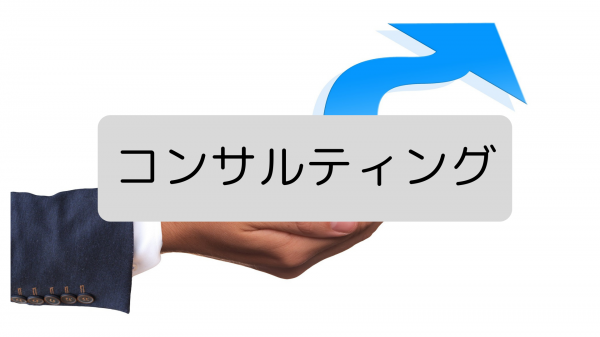ゆうやです!こんにちは。
今回は競馬場毎の特徴やコ-ス別のデータ、それに合わせて知って欲しい大切な考え方を説明します。
是非最後までご覧ください。
目次
競馬場毎の特徴、コース別データ

競馬場毎の特徴やコース別のデータを重要な部分のみ記載しました。
参考程度に読んで下さい。
札幌競馬場
・ほぼ坂による起伏が無い平坦なコース
・オール洋芝で若干時計がかかりやすい
・水はけが非常に良く重馬場に成る事すら殆どない
・全体的にコーナーが緩やかで大きく設定されており、丸っこい作りになっている。
その為、コースに占めるコーナーの割合が多く直線距離が短い(芝Aコースで266.1㎝)
・3コーナーから4コーナーにかけて捲りながら上がってくる馬の成績が優秀。
直線だけでの競馬では基本厳しくある程度のポジションは必要
函館競馬場
・ゴール板から1コーナーまでの距離が長めに作られている為、直線の長さは芝コースが262.1m、ダートが260.3mで全場のなかで最も短い
・3、4コーナーにスパイラルカーブが採用されている
※スパイラルカーブとは、入口から出口にかけて半径が小さくなる複合曲線によって構成されるコーナの事です。
出口のコーナーがきついため、外に振られる形になりやすく直線で馬群がばらけやすいという特徴がある
・直線が短いためセオリー通りある程度のポジションは必須で追い込み一辺倒の馬は厳しい。
・意外と起伏があるコース形態でローカルの中では一番の高低差(3.5m)がある。
スタートから2コーナー半ばまでゆったりとした下り坂。
その後、4コーナー入り口まで上り坂がなだらかに続く。
再度、直線半ばまで下り坂が続き、平坦となってゴールを迎える
高低差はあるものの基本はなだらかに上り、下りが設定されている
・オール洋芝であるが札幌程、水はけは良くなく梅雨の時期と重なる事もありタフさを求められる事が多い
福島競馬場
・前場の中で最も1周距離(Aコースで1600m)が短いコンパクトな競馬場
・3、4コーナーでスパイラルカーブを採用
※スパイラルカーブとは、入口から出口にかけて半径が小さくなる複合曲線によって構成されるコーナの事です。
出口のコーナーがきついため、外に振られる形になりやすく直線で馬群がばらけやすいという特徴がある
・起伏が二度もあるコース
平坦なイメージがある福島競馬場であるが実は坂による起伏が1周の中で二度もある。
スタートから2コーナーにかけてなだらかな下り坂(1.7m)
向正面では1.3メmの急な上り坂となる。
その後、平坦部分を挟み、4コーナーから直線(残り170m付近まで)にかけて再び緩やかな下り坂。
そして残り170メートル付近から残り50メートル付近まで、高低差1.2mの上り坂となりをゴールを迎える。
・開催が進み馬場状態が悪化していくと差し・追い込み決着が目立ちやすい
新潟競馬場
・日本唯一の直線競馬が行われる
・外回りの直線距離が658.7㎝であり日本の中で最長で内回りも直線距離は芝で358.7mもある
・3、4コーナーでスパイラルカーブを採用
※スパイラルカーブとは、入口から出口にかけて半径が小さくなる複合曲線によって構成されるコーナの事です。
出口のコーナーがきついため、外に振られる形になりやすく直線で馬群がばらけやすいという特徴がある
・外回りは直線で瞬発力勝負になりやすい
東京競馬場
・直線の距離は芝:525.9mダート:501.6m。
・コーナーの半径はゆっくりしている為、4コーナーでのごちゃつきは少ない
・上り下りが1周の中で2度もある起伏の激しいタフなコース
スタートから向こう正面にかけて1.9mの長い下り坂。
その直後から1.5mの急な上り坂に変わる。
少しの平坦が続き二度目の下り坂が3コーナー半ばまで続く。
そこから緩やかに二度目の上り坂が始まる。
直線460m付近から300m付近まで再度の急な上り坂となる。
直線残り300m付近から平坦となりゴールを迎える。
・幅員が非常に広いため、ABCDの4つのコースを使い分けることが出来、馬場の痛みを最小限に出来ている
・直線の末脚比べになる確率が高い
初めて東京競馬場に行った際、あまりにも中が綺麗でホテルのロビーにようだと感じたのを覚えています。
中山競馬場
・内回りは2、3コーナーがかなりタイト
・4大場(東京、中山、阪神、京都)の中で一番コンパクト
内回りの1周距離は1667.1mで札幌と大差なく直線距離は310mでありローカル場と大きく変わらないほどのコンパクトな競馬場
・1周の中での高低差が最大(5.3m)で特に、直線残り180mから70m付近までの高低差2.2mの坂は圧巻
全場の中でも高低差は断トツで高く(次は京都外回りの4.3m)2階建ての建物の高さに想定します。
・基本的に3、4コーナから競馬が動き出し上りがかかる決着になりやすい
・好位で競馬が出来ないと基本的に厳しい
初めて中山競馬場に行った際は、そのコンパクトさと直線の坂の高低差にびっくりしました。
中京競馬場
・2012年3月のリニューアルにより特徴が変わった
・標準以上に大きい競馬場
・芝の高低差も全馬の中で3番目に起伏が見られる(3.5m)
・新設された直線の坂により、かなりタフな設計
直線に向いてすぐの所から高低差約2mの上り坂。
その高低差2mの急な上り坂がゴールまで200メートル近く続く。
・3、4コーナーでスパイラルカーブを採用
※スパイラルカーブとは、入口から出口にかけて半径が小さくなる複合曲線によって構成されるコーナの事です。
出口のコーナーがきついため、外に振られる形になりやすく直線で馬群がばらけやすいという特徴がある
・馬場状態や開催時期、コースの特徴によりかなりタフ差が求められる
7月の梅雨の時期の開催、また馬場のメンテナンス時期が開催終了後に予定されている為、開催後半は馬場の劣化が目立ちパワーが求められる。
それに合わさってコースの特徴もあるのでタフさが必要になる場面が多い。
京都競馬場
・高低差4.3mの3コーナーの上り坂
京都競馬場名物3コーナーの坂はやはり特徴です。
向正面の半ばから3コーナーにかけて上り、4コーナーにかけて一気に下りそのまま直線に入る珍しい形。
・内埒沿いが空きやすくイン突きが決まりやすい
外回りの直線に3コーナーとの合流地点が設けられていることから、内埒沿いが空きやすい形態になっています。
その為、イン突きが成功しやすい競馬場の一つです。
・幅員が非常に広いため、ABCDの4つのコースを使い分けることが出来、馬場の痛みを最小限に出来ている
・インコースが有利になりやすい(特に一月開催の京都芝)
初めて京都競馬場に行った時は、あからさまに3コーナーの坂だけ目立っていたのを覚えていますね。
※2020年11月から2023年3月まで大規模な改修工事が実施される。
コースの線形に変更は無く坂も残される予定とのことです。
阪神競馬場
・外回りのバックストレッチが非常に長く3、4コーナーも非常にゆっくりと回れる
外回りの1周距離は2089mと東京競馬場より長く右回りの競馬場傳保最長です。
・直線距離も長い
外回りコースの直線は473.6mと右回り最長(新潟、東京に次いで全場3位)。
直線には坂もある。
・開催時期によってはタフさが求められる
幅員はそれほど広くなくコースの設定はA、Bのみ。
その為、馬場の傷みは進行しやすく、宝塚記念が行われる6月の開催は梅雨の時期という事もあり非常にタフなコンディションになりやすい
小倉競馬場
・コンパクトな競馬場でいかにもローカルらしい
1周距離は1615mで福島に次いで2番目に短い。
また直線距離も293mで坂も無く平坦、小回りのいかにもローカルらしい競馬場です。
・3、4コーナーでスパイラルカーブを採用
※スパイラルカーブとは、入口から出口にかけて半径が小さくなる複合曲線によって構成されるコーナの事です。
出口のコーナーがきついため、外に振られる形になりやすく直線で馬群がばらけやすいという特徴がある
・2コーナーにかけての坂
上記で平坦と書きましたがそれは直線の話です。
意外ですが芝コースの高低差は3m程もあります。
スタートから2コーナーにかけて緩やかな上りが続き、上った分をゆっくり2コーナーから向正面、3コーナーから4コーナーにかけて下っていく形になります。
・芝では特に逃げ、先行馬が多い
競馬場の特徴やコース毎のデータを予想に活かそう!

競馬場毎の特徴やコースごとのデータはいかがだったでしょうか?
僕なりに予想の要素として重要な特徴というのをまとめました。
競馬場と単に言えど様々な特徴・個性があり、それに伴って好走する馬のタイプも変わってきます。
ですので、上記でまとめた内容はあなたの予想に一役買ってくれると自負しています。
そして、それらを踏まえたうえで重要な事を説明します。
それは上記のようなデータに振り回されないようにしてください。
もちろんデータは参考になります。
しかしデータはあくまでデータでしかありません。
競馬予想における一つの要素でしかありませんので、競馬をトータル的に見て予想をする癖がとても大切です。

あなたの予想の参考になれれば幸いです。