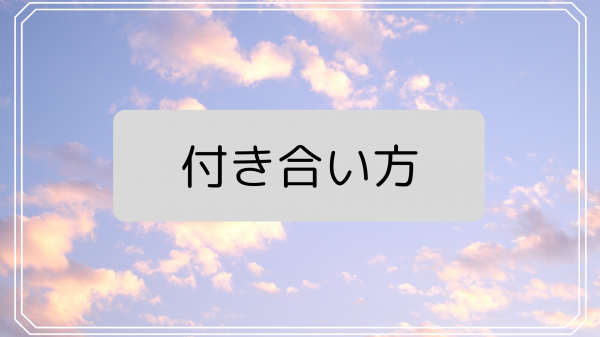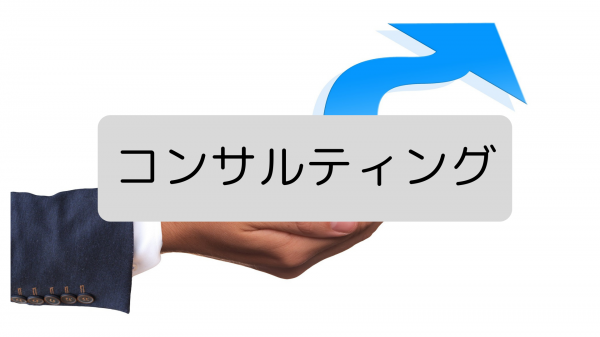ゆうやです!こんにちは。
突然ですがあたなは、競走馬の適性をしっかりと判断出来ていますか?
「この馬に2400mは長い」
「この馬は重馬場は走らない」
「中山巧者のこの馬が狙い目だ」
距離や馬場状態、コース等その馬に合った適正がありますよね。
しっかりとその馬に合った適性を見極められれば予想の質が向上します。
そんな競走馬の適性について今回はお話します。
目次
競走馬の適性とは

適性とは、❝ある事に適している性質や能力❞という意味です。
馬も人と同じで得意不得意があります。
その得意不得意は、距離や馬場の状態、競馬場の特徴など様々な要素に関わっているのです。まで
まずは競馬の予想をする上で、どのような適性を判断すればいいのか説明します。
距離適正
まず一つ目は距離適性です。
馬には自分に合った距離が存在します。
短いほうがいいのか、長いほうが良いのか、その間ががベストなのか。
同じ競走馬と言え、その馬に合ったベストの距離というのは本当に様々です。
JRAのレースで1000m~3600m(障害を抜く)まで距離が用意されている事からも想像が出来ますよね。
その為、その馬に合った距離適性を判断するのは競馬を予想するうえで重要な要素になります。
馬場適性
続いては馬場適性。
ここでいう馬場状態というのは、良馬場・不良馬場といった馬場の含水率による変化の事です。
「良馬場でしか走らない馬」
「重・不良馬場になればなるほど強くなる馬」
「芝が剥げている荒れ馬場を苦にしない馬」
この馬場適性も馬によって様々であり、レースの結果に直接結びついてしまう要因の一つになります
馬場が湿っていると全く能力を発揮できない馬も珍しくないですもんね。
その為、各競走馬の馬場適性を正確に判断することも競馬予想において重要なことです。
また、芝が得意かダートが得意か。
この大きなくくりも馬場適性により決まります。
コース適正
最後は、コース適正です。
中央競馬の競馬場は全部で10個。
そして、それぞれの競馬場に特徴があります。
中山競馬場には直線急な坂が用意されていたり、東京競馬場は芝の状態が非常によく時計が出やすい高速馬場であったり、新潟には直線コースがあったり。
その為、それぞれの競馬場の特徴にあった馬の適性が存在します。
少し古いですがトーセンラーという馬がいました。
あなたも知っているかもしれませんが、この馬は京都競馬場でしか結果が出ませんでした。
驚くくらい本当に京都競馬場でしか走らなかったのです。
この理由として、京都名物の3コーナーの坂を関係者が挙げていました。
京都競馬場のは3コーナーに坂が設けられており、小高い丘のようになっています。
その為、3コーナーから4コーナーにかけて坂を下りながら自然とスムーズに加速が出来る構造になっているのです。
そのスムーズに加速が出来て直線を迎える構造がトーセンラーには向いていたと話をしていました。
ここまで限局したケースはまれですが、少なからず馬それぞれに合ったコース適性は存在します。

適性の見極め方

ここでは上記で説明した書く馬の適性を見極める方法を述べていきます。
血統から判断。種牡馬や母父の成績を参考にする!
まずは血統です。
競馬はブラッドスポーツと呼ばれるほど、血統は競走馬の能力に影響を与えると言われています。
その為、種牡馬や母父、繁殖牝馬などの現役時代のレースを遡り調べる事で、その馬の距離や馬場の適性、得意な競馬場が分かることがあります。
しかし、血統で全てが決まる訳では勿論ありません。
キタサンブラックの距離不安説は有名な話ですよね。
競走馬の能力に影響が強いとされている母父。
キタサンブラックの母父はサクラバクシンオーで生粋のスプリンターです。
その事から、菊花賞や天皇賞春などの長距離レースでは特に「キタサンブラックには距離が長い」と言われ続けていました。
結果はあなたもご存じの通りです。
血統とは、その利便性と魅力から競馬の予想に多用されますが、万能ではないという事を思い直す良いきっかけになっていましたね。

馬体から判断する!
馬体からも距離や芝、ダートの適性を判断できます。
短距離向きの馬体。ピッチ走法の馬を選ぼう!
いわゆるピッチ走法の馬です。
ピッチ走法とは、1歩幅が短く回転数が速い走法の事。
胴や脚が短い馬に多く、一目見て筋肉質でがっしりしている印象を受けたら短距離向きの馬です。
長距離向きの馬体。ストライド走法の馬を選ぼう!
大跳びのストライド走法の馬に多いです。
ストライド走法とは、ピッチ走法の逆で一歩が大きくダイナミックな走りになります。
胴や脚が長い馬に多く、馬体を見てスマートな印象を受けたら長距離向きの馬です。
芝・良馬場向きの馬体。蹄は長く角度がついている馬を選ぶ!
芝コースはダートと比較して馬場が固いです。
また良馬場も水分を含んだ不良馬場などと比べて固い傾向にありますよね。
その為、着地の際に反動を受けやすいのでクッション性が馬に求められます。
クッション性は、繋ぎの角度と長さである程度判断出来るのです。
繋ぎとは、蹄と脚のをつなぐ部分の事で足首の役割があります。
この繋が長く角度もついていれば、その分だけ地面を蹴る推進力を得られやすい事になります。
故にダートより芝、不良馬場より良馬場向きの馬体ということになります。
ダート・不良馬場向きの馬体。蹄は短く立っている馬を選ぶ!
芝コースや良馬場とは反対にダートや不良馬場の場合、馬場自体にクッション性があります。
その為、関節部分が柔らかすぎると地面をしっかりと捉えられず全く走れません。
ですので、繋ぎは短く立っており、どこか歩容が固い馬の方がダート・不良馬場向きの馬体となります。

過去のレース結果から判断する。映像で分析する事で全てが分かる!
今回のレースの条件と同じ条件で走った事が過去にある場合、そのレースを分析する事でそれぞれの適性を判断出来ます。
ここでの間違いは、レース映像にて分析をせず結果のみで判断する事です。
「この馬は重馬場で勝っているから重馬場に適性があるだろう」
「過去に2400mで2着だから今回も2500mは問題ないだろう」
このように結果のみで判断するのはいけません。
なぜなら、適性がなくとも力の違いや展開利を活かして好走することは可能だからです。
「適性があるから勝つ」「適性がなければ走らない」
そんな両極端な話ではないのです。
その為、過去のレースを映像からしっかりと分析する必要があり、逆に分析がしっかりと出来ていれば1レースで全てが分かります。
個人的には、過去のレース映像にて分析する方法が一番性格だと思いますね。

レース映像にて分析をして適正を見抜きましょう!
いかがだったでしょうか?
今回は競走馬の適性にポイントを当てて、距離・馬場・コースの適性の考え方とい見極め方の方法を説明しました。
ポイントをまとめますね。
・競走馬には距離適性、馬場適性、コース適正がある
・血統から適性を判断する
・馬体方適性を判断する(走法や蹄の角度にて)
・過去のレース映像を分析する(結果のみでの判断はダメ)
今回の記事が少しでもあなたの参考になれれば幸いです。