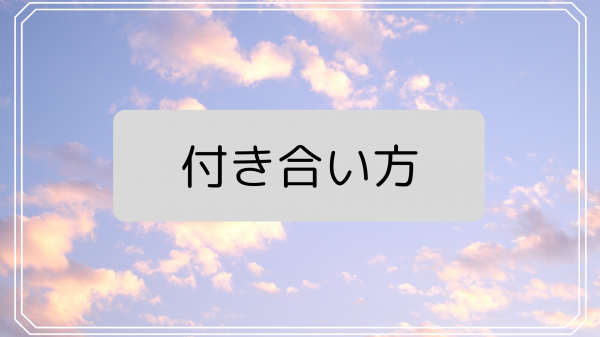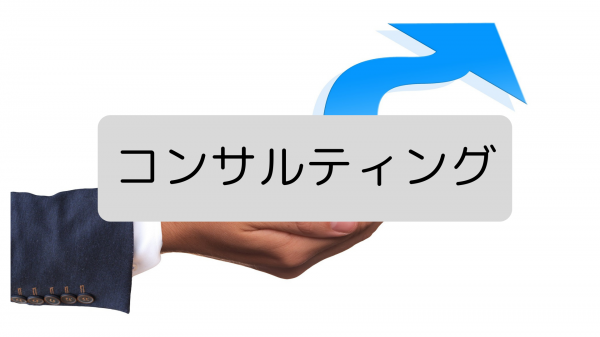ゆうやです!こんにちは。
突然ですがあたなは、競馬を予想するのにあたってラップを用いていますか?
「ラップなんて難しくて分からない」
「昔からラップの比較で予想をしている」
「そもそもラップって何?」
などなど意見が分かれると思います。
本日はラップを用いた予想方法、ラップ理論について説明をしていきます。
目次
ラップ理論とは?

ラップは競馬を予想する要素の一つとして既に確立されています。
しかしそのラップの使い方というのは人によって様々なのです。
ある人はペースを判断する為だけに使用したり。
ある人はラップの比較によって馬の優劣を付けたり。
ある人は上がり3ハロンを重要視してみたり。
その人その人のラップを用いた予想方法、ラップ理論があるのです。
どれが間違いでどれが正解というのは基本的にはありません。
それを踏まえたうえで僕なりのラップ理論をご紹介します。
ラップとは200m毎のタイムのこと
そもそもラップとは何なのでしょうか?
ラップとは200m毎のタイムの事です。
競馬のコースには200m毎にハロン棒という目印が立っています。
そして200m毎にその区間区間のタイムを発表しているのです。
そのタイムはレース結果としてJRAのホームページや競馬新聞などからも簡単に見れます。
また上がり3ハロンというの言葉をよく耳にする事があると思います。
上がり3ハロンというのは、ゴール前から3ハロン分のタイムを足したタイムの事です。
つまり最後の600mのタイムの事。
競馬ではこの上がり3ハロンを重要視する傾向が強く、上がり3ハロンが速いというのは強烈な末脚で追い込んでくるという予想に繋がるからです。
因みにネットでラップを調べる場合、多くが全体のラップと上がり3ハロンの表記のみしか書いてありません。
そもそもJRA自体が全体のラップと上がり3ハロンしか測定していないですからね。
その為中間のラップや最初の3ハロンの表記は分からないのです。
中間ラップや最初の3ハロンのラップは展開を考える上で非常に便利。
「どの馬が逃げるのか?」
という事を考える際、各馬のコーナーの通過順を参考にしがちですがこれでは不十分です。
レースによってテンが速い馬が複数いる場合、中間ラップや最初の3ハロンのタイムも参考にする事でより具体的に展開を考える事が出来ます。
最初の3ハロンは競馬専門紙には書いてありますので是非参考にしてみて下さい。
単純なタイムの比較は意味が無い
よくラップやタイムと聞くと
「この馬の前走のタイムが優秀だ」
「持ち時計がこの中で一番」
「レコードで走ったこの馬は強いに決まっている」
といったタイムでの比較をしてくる場合があります。
はっきりと言いますが競馬においてタイムというのは比較対象にはならないのです。
陸上競技でしたらタイムの勝負。
0.01でも時計が速い人がチャンピオンです。
しかし競馬ではタイムのみでの判断は絶対に出来ません。
その理由を後述します。
馬場によりタイムの出方は大きく変化する
一つ目は競走馬が走る馬場です。
競走馬が走る馬場というのは生き物。
競馬場によって
日によって
時間によって
天気によって
様々な要因により馬場は変化し、それに伴ってタイムの出方というのは大きく変わってきてしまうのです。
因みに今の日本の競馬は発展が目覚ましいです。
馬自体のレベルも上がっていますし、調教内容や調教施設も進化を遂げています。
その中で馬場造園家の努力もすごいです。
ガラスの脚と評される競走馬の足元に配慮をし、より安全に走れる芝コースを研究しています。
その結果、骨折により戦線離脱する馬や長期休養に入る馬、予後不良となってしまう馬が少なくなったと個人的には思っております。
特にここ1、2年は本当に骨折が見つかった馬というのは少なくなった印象が強いです。
実はその影響、タイムにも影響をしているのです。
最近の芝は以前と比べて以上に時計が出やすい。
定かではないですが、足抜きの良い固い芝の方が競走馬の足元には優しいらしいです。
そのため日本の芝コースは時計が非常に出やすい馬場に様変わりをしています。
特に印象深いのは2018年のジャパンカップですね。
アーモンドアイが3歳で勝ったレースですが圧巻んだったのは内容よりも走破タイムです。
今までのレースレコードだった2.22.2を大幅に更新する2.20.6の超絶レコードで優勝しましたよね。
これはもちろんアーモンドアイの強さもありますが、今まと比較して馬場が時計が出やすい形に変化してきている証明にもなります。
ペースによりタイムは自由自在
二つ目はレースのペースです。
レースの流れが落ち着きスローペースで淡々とレースが流れたら、そのレースが仮にGⅠだったとしても条件戦より遅いタイムにもなり得ます。
実際に2011年の有馬記念。
この年の有馬記念はオルフェーヴルが3歳で勝ったレースなのですが、歴史的な超スローペースの年でした。
その結果同日8レースの1000万下のレースより約3秒タイムが遅かったのです。
あの有馬記念が1000万の条件戦より3秒もタイムが遅いのです。
しかしオルフェーヴルが1000万の馬より弱いなんて誰も思いませんよね。
このようにペース一つでタイムというのは大きく変化が付けられるのです。
レースのラップを予想しそのラップに合った馬を選ぶ
ラップや走破タイムは比較対象にならないと分かったと思います。
それではいよいよ僕が推奨するラップ理論について説明します。
ラップ理論とはレースのラップを予想しそのラップに合った馬を選ぶ予想方法です。
ラップを分析する事で競走馬各々の能力が発揮しやすいレースパターンが見えてきます。
それを競馬予想に活かすのがラップ理論とです。
ラップ理論による競馬予想

それでは馬の適性を見抜くラップ理論での予想方法を説明します。
ここでは順を追って3つのセクションに分けて説明していきますね。
コースによるラップの特徴を考える
まず最初は予想するレースコースのラップの特徴を考えます。
競馬場はそれぞれ特徴がある造りをしています。
そのため競馬場毎の特徴的なラップの出方を示します。
もちろん全てのレースでそのラップの特徴が出る訳ではありませんが、馬の適性と結びつきを持たせるのに便利です。
特徴的なのは新潟競馬場。
コース立体図(左回り)
コース平面図(左回り)
www.jra.go.jp外部リンク
上の図を見てもらえたら分かるかと思いますが、外回りのコースは非常にバックストレッチ、直線ともに長いです。
バックストレッチが長いという事は、スタートしてから位置を取るのに余裕があるということ。
直線が長いという事は後方からの馬でも直線で間に合うということです。
このことから新潟外回りは、後傾ラップになりやすい事が想像できると思います。
後傾ラップというのはラップの後半部分が速くなるラップのことです。
つまり新潟競馬場の外回りは、上がりの速さが求められる瞬発力勝負になりやすいということが分かります。
この特徴を念頭に置きながら次のセクションへいきます。

過去のレースを比較しラップの傾向を出す
続いては予想をしているレースの過去のレースからラップの傾向を出します。
競馬ラボを使えば10年分の過去のレースが見れますよ。
その過去のレースを活用しラップの傾向を出していきます。
もちろん同じレースだからといって、今回も同じラップになる保証はありません。
ですのでここでは、あくまで「このようなラップになる傾向が強い」
というのが分かるだけで十分です。
レースの展開を考えラップの特徴を決める
ここからが本番です。
出馬表から
「どの馬が逃げるか」
「その馬が逃げたらどのようなペースになるか」
「先行馬はどこまで逃げ馬を追いかけるか」
などなど展開を考えていきます。
この時逃げ馬をベースに展開を組み立てていきましょう。
なぜなら逃げ馬が唯一ラップを作れるからです。
つまり逃げ馬によってそのレースのラップは決まるという事。
その為逃げ馬をまずははっきりとさせ、その逃げ馬がどのようなペースを作り上げるかを考えてラップを決めるのです。
この時に上記で説明した、コース毎のラップの特徴や過去のレースのラップ傾向を是非参考にして下さい。
ラップから馬の好走パターンを考える
最後は決めたラップに一番適性を持った馬を選択するだけです。
その馬が本命馬になります。
その為にはまず、競走馬の成績を見て過去に好走したレースに着目しましょう。
いくつもあると思うのでその全てのラップに目を通してください。
そうするとある共通点が見えてくると思います。
・前半3ハロンが後半3ハロンより1秒以上早い前傾ラップで好走するパターン
・直線に坂がある事で上りがかかるラップで好走するパターン
・上り3ハロンが32秒台の極端な後傾ラップで好走するパターン
などなどです。
挙げたらきりがありません。
好走するパターンというのは、その馬が能力を発揮させやすい状況であるということ。
この好走するパターンは馬によって顕著に分かりやすい場合もあれば、分かりにくい場合もあります。
しかし少なからずどの馬も持っています。
あなたが予想したラップで一番能力を発揮出来る馬を探してラップ理論は完成します。
ラップ理論を用いて回収率の高い予想をしよう

いかがだったでしょうか?
単純な時計の比較ではないラップを用いた予想スタイルがラップ理論です。
まずはコースや過去の同レースからラップの傾向を掴み、出馬表からレースの展開を考えラップを決め、そのラップで一番能力を発揮できる馬を探す。
もちろんはじめは慣れない事なので、ラップを見ても傾向や特徴を掴むのは難しいと思います。
そこは何度も実践を重ね、レース結果とのすり合わせを行っていきましょう。
慣れてきたらサクサクとラップが読み取れてきますよ。
ラップ理論を用いて競馬で儲けましょう。